ユーザ事例 & スペシャルレポート


ドリルデザインは、これまであったモノを見直し、リデザインすることで新しい価値を生み出すデザインを行っている。それは、デザインの本質的な作業かもしれないが、それを実践しユーザに新たなライフスタイルを提案することは簡単なことではない。またドリルデザインはインハウスを経験せずに独立した点でも、現在のデザイナーのあり方の先駆者的な存在ともいえる。ここでは学生時代からVectorworksを用いてデザインを行っているドリルデザイン代表の林 裕輔氏に、同社のデザインとツールについて語っていただいた。

林:僕は大学は経済学部で経済地理学を学んでいました。大学を卒業してデザインの専門学校(ICSカレッジオブアーツ)に入り、そこでインテリアデザイン、建築、家具などを学び、その同期4人でドリルデザインを立ち上げたのが2000年です。
林:僕は昔からモノを作ったり絵を描いたりとかが好きだったんですけど、フリーのプロダクトデザイナーの存在を知らなかったんです。こういう仕事があるというのは大学のときに知って(笑)。
大学のゼミでは、ある農村に行って調査をするとか、そういうフィールドワークをしていたんですが、地域、現地の経済的な問題など、調べれば調べるほどいろいろ出てきました。でも、学問の範囲内では現状分析まではするけど、解決策は国なり行政なり、あるいは建築家、モノを作る人が考えるということなんです。
そこで僕自身が、そういう問題解決も行いたいという気持ちがあったのと、当時、すごく不景気で、金融ビッグバンがあって大企業の終身雇用の信用が崩れたときだったんですね。経済学部だったので銀行など就職先はあったんでしょうけど、どこに入っても何か保証されるわけではなく、それなら何か自分でできることを身に付けた方がいいなということで専門学校に行きました。
その当時、デザインがちょうどブームになりかけの頃というか、イームズなどのミッドセンチュリーの家具が日本に入ってきて、こういった自由なモノ作りが行える、プロダクトデザインの仕事を知りました。
林:そうかもしれないですね。就職できなかったというのもあるかもしれないんですけど(笑)。でもほとんど成り行きです。
 専門学校を卒業して、あるコンペに作品を出そうと同級生で始めたのがドリルデザインの始まりです。最初の頃はグループ展やコンペに出すばかりでした。普通は、しばらくやってみてダメだったら就職考えようかみたいになるんですけど、続けられたきっかけとして、リビングデザインセンターOZONEのプロデューサーだった萩原修さんに出会えたことです。自己紹介で、デザインの学生で卒業したばかりなんですって言ってたら、「グループ展に出ない?」という話をいただき、そこでモビール展に出させていただきました。
専門学校を卒業して、あるコンペに作品を出そうと同級生で始めたのがドリルデザインの始まりです。最初の頃はグループ展やコンペに出すばかりでした。普通は、しばらくやってみてダメだったら就職考えようかみたいになるんですけど、続けられたきっかけとして、リビングデザインセンターOZONEのプロデューサーだった萩原修さんに出会えたことです。自己紹介で、デザインの学生で卒業したばかりなんですって言ってたら、「グループ展に出ない?」という話をいただき、そこでモビール展に出させていただきました。
僕らは、経験はないけど時間だけはあったんです。だから、1点だけの展示では面白くないから、自分たちがデザインしたモビールを100個くらい量産しました。それが2週間の展覧会で完売したんですよね。それでOZONEの人たちが気に入ってくれて、グループ展があると呼んでくれたり、展覧会の会場のデザインを任されたり、広がっていきました。「グラフィックもできる?」「やったことないけど多分できます」みたいな感じでした(笑)。依頼があれば、勉強しながらなんでもやろうというスタンスでした。それが2001年の頃です。
林:去年までは切れていたんですけど、デザイナーの村澤一晃さんがmother toolでモビールをデザインして、1つだけmother toolのラインナップにあってもどうしようもないからと、うちに「林くん、前やってたモビールやらない?」とお誘いを受けて、また動き出したんです。今は、どうせならモビールブランドを作りましょうという話で進めています。モビールはすごく面白いプロダクトだと思うし、部屋にポンと吊ってあると雰囲気が変わりますよね。でもその魅力はまだ浸透してないと思うのです。
キャラクターっぽいかわいらしい路線のものじゃなくて、もっとモダンで幾何学的な、どんな大人っぽい空間でもピシッと入っていくようなモビールを作りたいねという話なんです。
林:そうなんです。アイデアも入れられるし、純粋に彫刻っぽい、オブジェとしても楽しめます。
林:まあそんなことをやっていて、それでぽつぽつ仕事が入るようになって、初期の頃は地方の、特に四国の仕事が多かったです。たまたまOZONEで四国のメーカーと東京のデザイナーのマッチング事業みたいな企画があって、「TRASH POT」という紙製のゴミ箱を松山の会社で作って発表しました。
それを四国の東予産業創造センターの局長が気に入ってくれて、いろいろな会社を紹介してくれました。それが2004年、2005年頃です。アッシュコンセプトと出した積み木の「ヒューマンブロック」も高知で作っていました。
林:転機になったプロダクトというのでは、今「合板研究所」で新しい素材を作っています。
林:はい。合板、プライウッドですね。普通は木目を交互に挟んで板を作っているんですけど、そこにいろいろな素材を挟んだら面白いんじゃないかということで、FULL SWINGという東京・多摩にある木工所の人たちと、合板は可能性があるからいろいろなもの挟んで実験してみようと合板研究所を立ち上げました。
毎月、挟みたい素材を持って集まるワークショップを行っていて、アクリル、樹脂系、布系、発泡剤とかいろいろなものを挟んだ中で、偶然印刷所で分厚い、小口まで色の入った紙を見つけたんです。その紙を挟んでみたらかなりいい。新しい使い方、可能性を想起させるんです。これまでの合板は、小口をいかに隠すかという発想でしたが、逆に小口をどう見せるか。どういうふうにカットしたら面白い見え方がするかとか、そういうことを想起させる新しい素材が作れるんじゃないかというので。これは「Paper-Wood」の名称で商品化されました。
そもそもインテリアライフスタイル展のneONというコーナーに出展し、そこで北海道の会社が気に入ってくれて、そこでまた1年ぐらいかけて実験や強度試験などを行い、2010年に商品化されました。その年のグッドデザイン賞もいただき、現在はインテリアの棚板やテーブルの天板、住宅の階段の板などいろいろな場所で使われるようになっています。
これは今までプロダクトとかモノを作っていた中で、何か素材からモノ作りができないかというのでやって、すごく可能性を感じているんです。「Paper-Wood」をうちの作品として家具にするという方法もあったんですけど、誰もが使える素材として流通させたほうが広がっていくし、可能性があって面白いですよね。
林:最近は家具のデザインをしていて、VILLAGEという椅子がTIME&STYLEという家具メーカーから出ています。これはウィンザーチェアという形式をベースにしているんですけど、日本の空間に合う椅子を作ろうというシリーズです。家具のデザインはすごく楽しいというか、もともと家具を手がけたかったんですよね。
林:そうです。ただ、他のプロダクトデザイン系の事務所と違うのは、うちはトータルで全部できるという点です。例えばコップを1個デザインしてそのメーカーのラインナップに加えて終わりという単品の依頼はそれほどなくて、どちらかというとあるシリーズを作ってほしいとか、何かしらの世界観なり全体的な見え方の受注が多いです。
グランドで勝負するというか、ようするに、見本市で展示する場合はブースの空間デザイン、カタログなどのグラフィックデザインまで行います。
林:はい。単体デザインもよいのですが、ラインナップや流通まで含めて提案したほうが、良い結果が出ると思いますので。
林:いきなり独立してしまったので、できることは全部受けようということですね(笑)。プロダクトだけでなく、グラフィックも空間デザインも受けます。そして今は素材のデザインまでできたら面白いねと、幅を広げ、俯瞰で眺めながら、1つ1つもちゃんとフォーカスしていきたい。そういう活動を意識せず自然に行えるのがいいなと。
 林:フォルムに関しては、整えるのは本当に最後なんですよ。それより構造的なことをやりたくて。初期のジョウロ、スコップもそうでしたが、まず今のジョウロとかスコップの構造自体を疑ってみて、このほうが合理的なんじゃないかとか、こういう構造にするとこういう機能が生まれるんじゃないかとか、そのへんからスタートすることが多いです。最終的な線や比率は、調整できる範囲内で最後に整えるという感じなので、いきなりディテールから入ることはあまりないですね。
林:フォルムに関しては、整えるのは本当に最後なんですよ。それより構造的なことをやりたくて。初期のジョウロ、スコップもそうでしたが、まず今のジョウロとかスコップの構造自体を疑ってみて、このほうが合理的なんじゃないかとか、こういう構造にするとこういう機能が生まれるんじゃないかとか、そのへんからスタートすることが多いです。最終的な線や比率は、調整できる範囲内で最後に整えるという感じなので、いきなりディテールから入ることはあまりないですね。
林:そうです。例えばモノは決まっていなくて、ただ新しい加工技術や素材だけがあるときは、この素材はどんな構造にすれば一番活きるかとかいうことを考えながらデザインします。
林:最初にモビールを手がけたのがよかったのかもしれないです。例えばプラスチックの型物ばかりを最初からずっとやっていると、どうしても表面のハリ感とかフォルムの曲線とか、そういうディテールの方にどんどんいってしまう。でもモビールは完全な構造体でしかなくて、当時製造工場を知っているわけではなかったので、どうやったら釣り合うかとかどんな構造を作っていくかみたいなことを、手作りでいろいろ試みました。
設立当初の依頼は小さなプロダクトが多かったので、構造の試行錯誤が行いやすかったんですね。なので、自然とそういう感じになりました。家電メーカーなどのインハウスに入っていたら、また違う発想法だったのかもしれないですね。
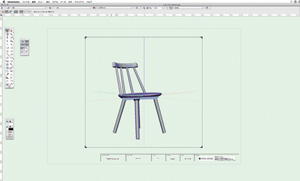 林:Vectorworksは、前身のMiniCAD7の頃から使っています。学生の時からなのでもう14年くらい前ですか。専門学校で導入していたからというのがきっかけですが、卒業制作とかで必要になるので、自分でも購入しました。それ以来Vectorworksをずっと使っていますが、設計事務所ともまた違ってガッツリは使わないので、全然使いこなせていないと思います(笑)。
林:Vectorworksは、前身のMiniCAD7の頃から使っています。学生の時からなのでもう14年くらい前ですか。専門学校で導入していたからというのがきっかけですが、卒業制作とかで必要になるので、自分でも購入しました。それ以来Vectorworksをずっと使っていますが、設計事務所ともまた違ってガッツリは使わないので、全然使いこなせていないと思います(笑)。
林:そんなに大したスケッチも描かないです。こんな構造にしようかなとか、こんな断面形状にしようかなというのを、メモみたいなものから入って、次にだいたい模型を作ります。
林:製造用の図面は本当に最後の段階ですね。模型用の図面はIllustratorでササッと描く場合もありますが、家具デザインの場合は、ほとんどVectorworksですね。シンプルな形だったらVectorworksで3Dまで起こします。
林:プレゼンテーションは模型が多いです。原寸の模型。手とスタイロカッターとかで、木はカンナで削ってテーパーをつけてとか自分で行っています。まあざっくりですね。
林:ほぼ同時進行でパーツ図を起こしていきます。それを組み合わせてVectorworksで図面を描いていくという感じですね。
林:モノによってですね。例えば、光造形や3Dプリンタでモデルを作ることが前提だったり、金型データとして加工する場合は、別のソフトを使っています。
 --Vectorworksと他のツールを混在させて使う場合もあるのですか。
--Vectorworksと他のツールを混在させて使う場合もあるのですか。林:デザインの領域は多岐にわたるのでVectorworksはかなりの頻度で使います。家具、空間はほとんどVectorworksです。逆に3Dの3次曲面を多用する場合はRhinocerosを使いますし、展開図などが必要な紙のプロダクトや布モノはIllustratorで描いていきます。空間系の仕事とかではShadeもけっこう使います。VectorworksとIllustratorとShadeは連携する場合もあります。
林:今、Vectorworks2012を使っているんですけど、使っている機能は一部ですね。慣れていることもあって、レンダリングはShadeに持っていったりしています。パーツの平面をEPSで取り込んで、それをShadeで加工して3Dにして組み合わせていくことが多いです。
林:例えばメルセデス・ベンツ コネクションのために作った椅子などはVectorworksでないと書けない感じでした。この椅子は三方継をしているんですけど、継ぎ目の角度をピシッと合わせるとかはVectorworksがいいですね。また、VILLAGEという椅子の図面では、パーツが細かくて、穴の開け方とかも21度振ったところに23.5度の穴を開けてくださいといった指示が入ります。
林:メルセデスの椅子も、50角から始まって27度、28度とか使います。角材でつないでいくのですが、この辺は工場に丸投げできないので、すべてVectorworksでパーツ図で描いているんです。
林:原寸で模型を作るということはパーツ図を描かないといけない。そうすると、結局ここまでやらざるを得ないみたいなのはあるんです(笑)。
林:むしろ、これはできないって言われるかなと思いつつ出した図面でも作っていただけることがあります。メルセデスの椅子は工場の担当者に、これは今まで作った椅子の中で3本の指に入る難しさだと言われたそうです(笑)。
技術の高い工場だと難しいほうが職人さんのモチベーションが上がることもあって、デザインサイドでできるできないの判断をシビアにやらない方がいい場合もありますね。最低限、木材の動きの逃げをどこに持たすかとか、そういうことは考えます。それでパーツ図を描けばだいたい作ってもらえます。
 --現在、Vectorworksへのリクエストはありますか。十数年使われてきて、自分のワークフローやデザインワークの中で望む機能などがあればお聞かせください。
--現在、Vectorworksへのリクエストはありますか。十数年使われてきて、自分のワークフローやデザインワークの中で望む機能などがあればお聞かせください。林:素晴らしいソフトだと思っています。あえて言えば、Vectorworksだけで手軽にきれいなレンダリングができたら、言うことないですね。
林:そうですね、Shadeの操作性に慣れてしまっているので、今度、Vectorworksでレンダリングしてみます(笑)。素材感とか光源の感じとか難しいなとか思っていて。
林:あ、そこまでできるんですね。すみません、勉強します(笑)。
林:あります。できれば1本のソフトで全部できたら理想だとは思います。ただ1本にまとめきれないのはやはりクライアント対応がありますからね。図面に強い、金型に強い、印刷に強い、それはやはり各ツールの存在価値になっているので、当面はその分野で一番馴染んだツールをそれぞれ選択していくことになるのかと思います。
【取材協力】
ドリルデザイン http://www.drill-design.com
林 裕輔 氏
この事例はカラーズ有限会社の許可により「pdWEB」で2013年6月3日より掲載された記事をもとに編集したものです。
記載されている会社名及び商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。 製品の仕様は予告なく変更することがあります。